毎日新聞−2000年(平成12年)12月10日(日)
いのちの時代に
「末期医療」課題重く 「在宅死」思い揺れ
| 先端的な生命科学が変える末期医療の現場で、いのちの尊厳や患者の自己決定権、がんの「告知」の問題などを追った社会面の連載「いのちの時代に−第4部 静寂のかなた」(11月)に、多くの反響が寄せられた。限りある生命をどう全うし、「死」という現実をどう受容していくのか。自身や家族の体験をつづった投書の内容は、ひときわ重く、深い。取材記者の報告とともに、それらの一部を掲載する。 【「いのちの時代に」取材班】 |
末期医療では盛んに「QOL」(クオリティー・オブ・ライフ=生命の質)という言葉が使われる。生命維持装置などで生かされるのではなく、いかに自分らしく生きるか。そこに、在宅医療が支持される理由があるのだろう。しかし、個人の家にまで機械は入り込みつつある。そのとき、自分ならどうするか。そう考えながら、私(記者)はこの取材を始めた。
□ □ □ □ □ □ □ □
「妻の心臓は動いている。生きているんだ。水(点滴)をやらずに、死ぬのを待つというんですか」
ほとんど意識のないままベッドに横たわる恭子さん=仮名=を前に、夫は顔を真っ赤にして怒鳴った。点滴をしても、衰えた細胞は栄養分を維持できない。それがもとで腹水や胸水がたまり、全身は水ぶくれのようになっていた。それでも、家族は延命にこだわる。医師の西村知里さん(31)はつらかった。
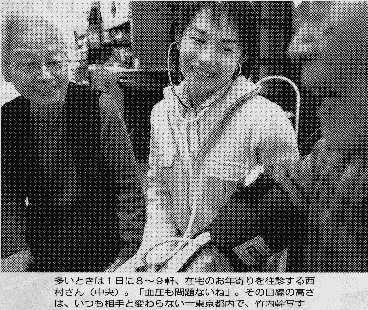 末期の肝臓がんと診断され、自宅での最期を望んだ恭子さんから、西村さんは以前「少しでも楽になりたい」と頼まれていた。医師の考えを押し付けることはできないが、患者を苦しめるだけの点滴はしたくなかった。しかし、点滴中止を打診する西村さんに、家族が出した答えは「ノー」だった。
末期の肝臓がんと診断され、自宅での最期を望んだ恭子さんから、西村さんは以前「少しでも楽になりたい」と頼まれていた。医師の考えを押し付けることはできないが、患者を苦しめるだけの点滴はしたくなかった。しかし、点滴中止を打診する西村さんに、家族が出した答えは「ノー」だった。
「苦しいですよね。ごめんなさい」。心の中で泣きながら、点滴の指示を出し続けたことを覚えている。1998年7月のことだ。
□ □ □ □ □ □ □ □
「妻のことでお会いしたいんですが」。西村さんが電話を受けたのは、外来診療中の夕方だった。白髪交じりの中年男性は、末期がんの53歳の妻が在宅医療を望んで退院間近なこと、往診をしてくれる医師を深していることを話した。その患者が恭子さんだった。
西村さんは大学を出て、麻酔科などで2年間の研修をした後、開業医の父親のもとで地域医療の現場に飛び込んでいた。研修中、医師の目線の高さに違和感を覚え、大学病院を辞めていた。恭子さんの前に、5人の末期患者を在宅でみとってきた。自信はあった。
ところが、病状の進行は想像を超えていた。退院するとき、すでに口からの栄養補給ができなくなっていた恭子さんは、鎖骨下の太い静脈に点滴の管をつないだIVH(中心静脈栄養)をつけたまま、自宅に戻った。意識は徐々に薄らいでいく。本人の意思を確認できない現実が葛藤を深めた。点滴をやめて、安らかな最期を迎えさせてあげたいと思う西村さんと、目の前の生命に執着する家族の願いは、すれ違った。
何度も話し合い、点滴の量を必要最小限にすることには同意してもらった。しかし、点滴で膨らんだ体に利尿剤を入れては、おしっこを出させるという矛盾した作業は、最期まで続いた。「これでは延命至上主義の病院と変わらない」。西村さんにはそう思えた。
□ □ □ □ □ □ □ □
自宅での療養を始めて18日目。恭子さんは54回目の誕生日を迎えた。日付をまたぐのは難しいと西村さんが考えてから、4日が過ぎていた。長女らの手作りのバースデーケーキと、たくさんの花が飾られた部屋に足を踏み入れたときのことだ。空気が、どこか違っていた。家族から死への恐怖が伝わってこない。目が穏やかになっている。
「家族は、どうしても誕生日を迎えさせてあげたいと思っていたんだ。そして、その愛に応えるために、恭子さんは頑張り続けてきたんだ」。西村さんは、そのとき、初めて理解できたような気がした。在宅死の意味を頭だけで考えていた自分に気付かされた。
誕生日の翌日、恭子さんは眠るように息を引き取った。しかし、最期まで点滴を続けた体はパンパンに膨れ、「陸の上の溺死」そのものに思えた。「家でみとれてよかった。母も喜んでいると思います」。別れ際、長男はそう言って頭を下げた。だが、決して晴れやかな表情ではなかった。今も、末期患者への点滴には賛成できない。ただ、在宅死の在り方は一通りではない。西村さんは、そう考えるようになった。
【千代崎聖史】